
こんにちは。nemu(@nemusblog)です。
今回は特に国際協力のキャリアと、メンタル管理のことについてまとめてみたいと思います。
国際協力分野について、キャリアの歩み方についての素敵な情報は溢れていますが
日本生まれ・育ちの非ネイティブが海外で国際協力の仕事をするのってなかなかに精神面が強くないと厳しいなと日々感じています。
今日は、そんな敢えて厳しいキャリアを選びながらも、メンタルを保つべく取り組んでいることたちについて記事にしました。
Contents
国際協力キャリアにメンタル管理が必要だと思う理由
①定期的に生活圏、環境が変化する
多くの仕事が2〜3年契約となるこのお仕事。
話せる言語や専門分野によって、◯◯地域専門、◯◯分野専門と絞られてはいきますが、
一つの国の一つの地域だけのプロジェクトにずっと関わることはそんなに多くなく、定期的に暮らす国や地域が変化していきます。
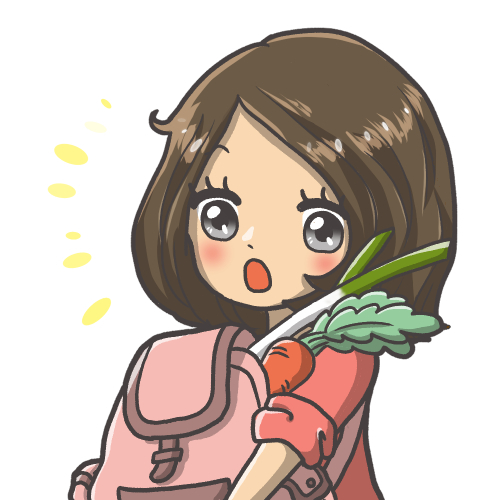
やっとできた友達と離れ、違う宗教、言語、食事、インフラの地域で1から生活を作っていくのは
楽しさもある一方、時にふと寂しくなってしまいます。
「ここの一員だ」と感じるまでに数ヶ月かかったり、最後までなんとなく馴染めず部外者感から抜け出せなかったり。
思い出の場所があるわけでも、落ち着けるテレビ番組があるわけでも、戻ってきていいよと言ってくれる家族がいるわけでもない。
その地域ごとに治安状況も異なるため、活動範囲も国や地域によってめちゃめちゃ影響されてしまい、自由に外で気分転換ができなかったりもします。
 【海外現地採用】新卒就職でカンボジアを選んで良かったこと
【海外現地採用】新卒就職でカンボジアを選んで良かったこと
②なかなか生活が安定しない
海外の大手NGOで勤務したり、国連などに入り経験を重ねた先輩方は安定していくのでしょうが(願)
若手で現場希望だと、競争率も高く、短期や無給で始めることも少なくないと感じます。
数ヶ月後には仕事がない、良い経験はできているけれど経済的に不安定….という状況に陥ることも多々あります。
そして正社員雇用が多くないので数年ごとの就活。一生就活…..
2年以上の途上国経験や海外大学院留学などが求められることが多いため.、
プライベートとの両立も難しく、恋愛や結婚、出産などをどうするか?はずっと付き纏う懸念事項です。
そんな先が見えづらく、頼れる軸を持ちづらい中で、毎日ピヨピヨと楽しむことは…なかなかに難しいです。
③外国語ネイティブに囲まれて仕事をする必要がある
非ネイティブの言語で仕事をする場合、やっぱり勉強してもわからないことは溢れていて
常に自分との戦いで、これが結構大変だなと私は日々落ち込んでいます。頑張ってもなかなか成果が出ない。
自分が頑張って達成できる最大限と、所属組織で求められている最低限に、まだまだ差がある気がしてしまう。
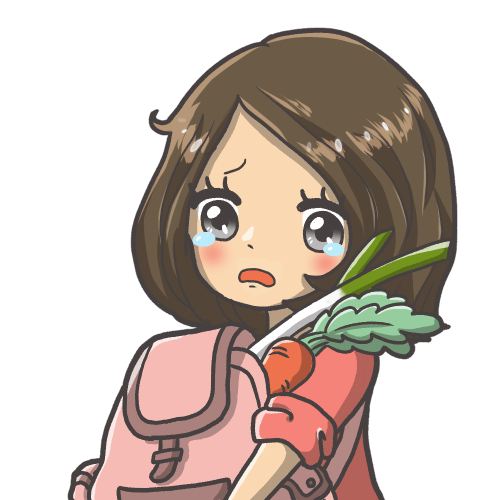
頑張れてないんじゃないかと自分に言い聞かせていましたが、その手法だと自分が折れそうなのでやめました。
帰国子女や、親がお金を出してくれて留学して、気づいたら語学はできていました、という方の姿を見て羨ましいなと思ってしまうことも多々あります。
そんなバックグラウンドの差がなく働ける業界であってほしいけれど、、、しがみ付くにはまだまだ厳しそうです。
④途上国、僻地….大切な人にすぐ会えない
特にこのコロナ禍で、海外に出ている人は家族や恋人に会えずに辛い思いをされたのではないでしょうか。
時差があったり、停電が多い地域だったり、電波が安定していなかったり….いつでもネットで声が聞けるというわけでもなく。
フィールド業務では首都から離れた街などへの派遣なども多く、海外で働くことを選んだ上とはいえ、
日本直通の便がある先進国の大都市というわけではないので遠く感じてしまいます。
支えてくれる人がいたら、大変な中でも頑張れるけれど。
そこのバランスはキャリアを選ぶ上で意識していく必要があると強く感じます。
 国際キャリアで通用する、職歴と学歴の重ね方
国際キャリアで通用する、職歴と学歴の重ね方
⑤同世代の仲間を作りづらい
20代で現場に出て、一人で暮らしている日本人女性などなかなか多くなく。同期がいたことがありません。
この国に日本人は何人いるんだろう、同じ歳なんているのかな…と思いながら過ごした地域もあり、
出会えた時はめちゃめちゃ嬉しいですが、そんな素敵な出会いはとても貴重なもの。
共感してもらえる、って日々頑張る上ですごく大切だと思うのですが、そんな「わかるー!」を言い合える人に出会うことは簡単ではないです。
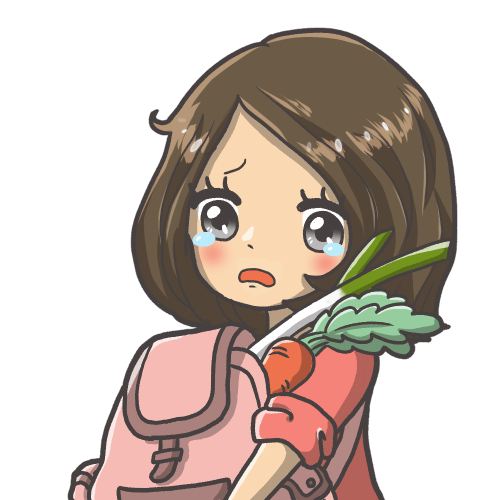
⑥自分の”日常”だったものがない環境で成果を出さないといけない
自分が良いパフォーマンスを出せるのって、様々な要因が絡み合っていたりします。
支えてくれる人、落ち着ける家、慣れた味、頭を使わなくても口から出てくる言語、体調を崩さない気候、、、想定外のストレスがない生活、などなど。
そういうのが一切ない環境にぴょんっと飛び込んで、期待通りの成果を出すことが求められる仕事。
評価してくれる上司や、相手側組織が自分の文化圏と大きく異なることもあり、
これはおっけいだったのか!?その反応はポジティブ?ネガティブ!?本音は?!??など
把握するのが容易ではなかったりして、自問自答を繰り返すことも。
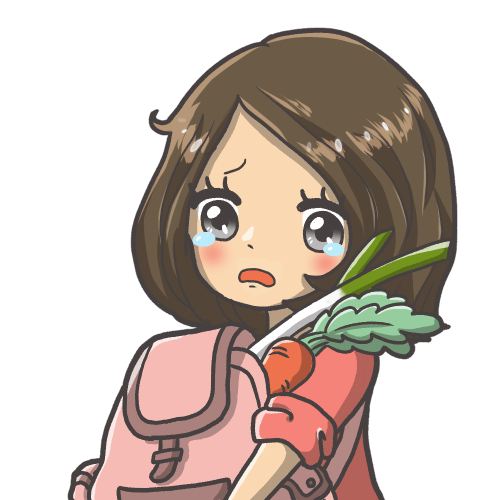
⑦「すごい」と言われることと現実のギャップ
国際協力分野はやっていることがわかりやすくスケールが大きい印象もあるのか、
周りの人からは良い印象を持っていだけることも多いのが事実。
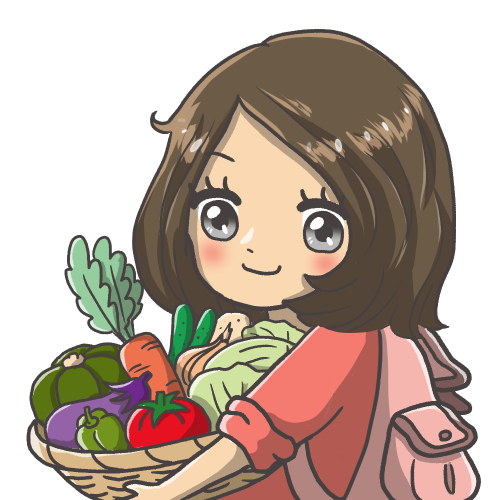
誰かによく思われたくて仕事をしているわけではないけれど、応援してもらえることはとてもとても嬉しいです。
ただ、その”周りから見てすごい”と、上記の通り成功なんて程通い”実際の自分”のギャップは、すごく感じてしまう。
「海外に暮らしてるなんていいね!」「英語を使って働いているのはかっこいい」など言われるたびに、
あれ、この生活って、そんなキラキラしているはずのものなのか?楽しめていない私はやばいんじゃないか?と自己否定に陥ってしまいます。
多くの人が憧れている生活ができているのに、それを心から楽しめずに毎日不安ばかりが続くと、
どこに行っても幸せになれないんじゃないか…?と途方に暮れることもあったりします。
もちろん、楽しいことや幸せを感じることもたくさんたくさんあります。
だから、これからもずっと続けていきたいと思っています。
でも、ライフワークにするため乗り越えるべき試練があまりにも多くて、そんな幸せや嬉しさを見失ってしまう時もあるという話です。
まとめ:それでも憧れ続けた仕事だから
….だいぶ溜まっていたみたいでぶわっと書いてしまいました。
実は大変な理由よりも、それをどう工夫してるかの記事にするつもりだったのですが、文字数が溢れそうなので一旦終わりにします。
こんなネガティブなこと言わないで!と思う学生さんや、実際そんなことないです、という先輩方もいらっしゃるかもしれません。
私個人が難しいな、と感じていることをまとめたのみですので、そこはご了承ください。工夫されて乗り越えられたアドバイスなどあれば、ぜひ教えてください。
 【無料】イギリスで地元のメンタルセラピーを受けてみた話。
【無料】イギリスで地元のメンタルセラピーを受けてみた話。
どんなお仕事にも大変なことはありますが、国際協力分野は憧れやキラキラした印象が自分自身も大きかった分
悩みや葛藤も記録していきたいと思っています。
次の記事では私が工夫していることをまとめます…こっちがメインの予定だったのに。泣


